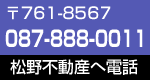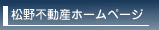|
2023,06,30, Friday
さぬき市志度・津田・石田の県立3高校を統合して新設する高校について、淀屋圭三郎県教育長は29日、さぬき市造田是弘の青木池南のJR造田駅南約1キロ(徒歩13分)の場所に整備すると明らかにした。この場所であれば、琴電長尾線長尾駅(徒歩28分)も使えなくはないか。6.2ヘクタールの農地などを取得し、校舎や運動場、農業実習用地を配置する。
予定地の中央部分に校舎や地域連携施設などを整備し、北部分に運動場や体育館などを配置する。一方南側には、農業実習用地を置く。県立高校では初めて整備する地域連携施設は、地域との共同作業や小中学生を対象にしたものづくり教室、実習で生産した農産物の販売などに活用する。統合校は、3校の普通、農、工、商、家庭の5学科を引き継ぐ総合高校で、規模は1学年8学級を想定している。 随分前から、志度・津田・石田の県立3高校の統合計画は言われていて、少子化からも避けられないとは考えていました。建設予定地は、さぬき市の中央に位置した田園風景のひろがる広大な農地。周りには何もないし、開発工事には障害がないと思われます。新設校には期待が膨らむのですが、閉鎖する旧校舎群はどうなるのか。 廃校舎はまだ十分使える建物で、何かの受け皿が出てくるのではと期待するのですが、やはり閉鎖は寂しさを感じる。近代日本では人口減を経験するのは、ここ10年位のことで、それでもまだ実感はない。緩やかに減少するなら、慣れもついてくるが、自分の活動範囲も狭まってきている。頭の中を切り換えて、『縮小』ポジションを考える機会としたい。世界的に見ても日本国土に、1億2千万人が暮らすのは狭いなと感じる。 3つの高校が閉鎖になると、周辺の町も随分変わってくる。人の流れが絶えて、閉店する店舗も出てくるだろう。建物も解体されて、空地も増えてくるが、見通しも良くなる。車を置くには、随分便利になります。道路拡幅まで進むと良いと思いますが、民間ではせめて建物解体まで、その後は県市町が担うことになるが、市町も税収が縮小気味だ。考えすぎも身体に良くない。まずは新設校に期待を込めて、見守りたい。 |
|
2023,06,29, Thursday
オイスカの活動に協力し、多少の国際協力に貢献できていると自負している私ですが、本日の来店客に『技能実習生』を見ました。インドネシアからのイスラム教徒の男女二人。日本に住んで、近くの企業で働いて技能を収集しているそうです。男女は来日3年目、日本語もかなり出来ます。弊社の賃貸アパートへ入居するという二人に割り込んで、就業先の総務担当者とも、名刺交換して情報交換をしました。初めての経験です。
ムスリムの男性は自由な服装ですが、女性のイメージは、全身黒い服で覆われているというものではないでしょうか?これは、イスラム教の教えによるものと思われていますが違います。これは、イスラム教における「女性は自分の美を親族以外の男性に見せない」というルール。そのため全身を覆っている服装が多いのですが、黒でなくてはいけないという決まりはありません。意外かもしれませんが、服装は自由です。急ぎホームページから、情報を得ました。 今日の『技能実習生』も男性はラフな服装で、女性もスカーフ以外は同じ恰好でした。スカーフを何と呼ぶのかさえも知らないのですが、この女性は黒でした。昨年のオイスカ研修生のインドネシアからの『サンダ』さんは、色は多色でしたが、常にスカーフをしていました。遊んでいる時も、個人差が随分あるようでした。 日本国の『技能実習生』制度には、開発途上国から来る技能実習生に対し、業務を通じて日本の技能・技術を学び取ってもらい、帰国後、実習生本人の職業生活の向上や経済産業の発展に貢献することを目指して指導するように書かれています。技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。 研修期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。 受け入れる方式には、『企業単独型』と『団体監理型』の2つのタイプがあります。 2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。 技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。) 主流の方式は「団体監理型」で、営利を目的としない協同組合や商工会などの監理団体が技能実習生を受入、実習実施機関となる加入企業で技能実習を実施する方式です。もうひとつの「企業単独型」で、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入て技能実習を実施する方式となります。公益財団法人 国際研究協力機構によると、2016年末の時点で団体監理型の受入が96.4%、企業単独型の受入が3.6%となっています。益々「団体監理型」となっているようです。 私の中では企業が、日本人若年労働者が働かないのに業を煮やし、外国人労働者に頼る相互関係が出来ているように感じています。先の二人はやがて結婚する予定と聞きましたが、労働環境次第だと私も思います。家賃も安くなり、技能実習生の収入でも生活していけます。このような職場ばかりではないのかもしれませんが、以前言われていたような劣悪環境での生活は、改善されているようです。 技能実習生が弊社管理物件に入居していたとは知らなかったのですが、オイスカ四国研修センターでも、「団体監理型」の教育組織として、技能実習生の日本語研修にあたっています。オイスカは、技能実習生も海外研修生も日本語教育など初期教育では同一視しています。来店の彼らもオイスカのことは知っていて、派遣斡旋の総務さんも私のこと、オイスカのこともよくご存じでした。 |
|
2023,06,27, Tuesday
最近アウトドアー関連用品に、目が行くようになっています。小中学生の頃、友と戸外で食事をしたり、簡易テントで寝泊まりしたことがありました。今のように携行具が小型軽量化されてなくて、徒歩や自転車で行くキャンプは、大変でした。それでも楽しかった。何人かで行くのが楽しみで、将来の夢などを語っていました。『ひとりキャンプ』の醍醐味は、この年でも理解できません。ひとそれぞれですね。
そんな折、グッドデザイン賞(日本デザイン振興会主催)の2022年度受賞結果が(2022年10月)7日発表され、愛媛県内ではタオルから生まれた着火剤「今治のホコリ」=写真=など3件が選ばれた。という愛媛新聞の記事を見つけました。もう半年以上も前の報道ですが、私はここに趣味の喜びと企業経営の芽を見いだします。 西染工(今治市)の「今治のホコリ」は染色工程後の乾燥機内で出たさまざまな色の廃棄物「ほこり」を、アウトドアーで使う着火剤として生まれ変わらせた。地場産業の廃棄物でサステナブルな商品をつくり、見て楽しめる使いやすい製品となっていることなどが評価された。と新聞には書かれていますが、SDGs(持続可能な開発目標)からもナイス商品ですね。これまでの廃棄物が、商品として稼いでくれる。 キャンパーからすれば、登山でのキャンプ荷物は限りなく軽量化したい。しかし夏場でも、食事は温かいモノを食したい。バーベーキュにしても、火をおこす作業が難題です。この「今治のホコリ」を着火剤として使うアイディアは、軽量なおかつ確実性から抜群ですね。正確にはまず着火機である『マッチ』や『ライター』『火打ち石』から『種火』を得て、それを新聞紙やティシューペーパに移しますが、ここで先の「今治のホコリ」が登場します。 タオル製造の過程で出る『ゴミやほこり』の『ほこり』を使います。着火しやすく、すぐに燃え広がります。どうしてもタオル製造過程で出るモノで、防ぐことが出来ない厄介者でした。高速回転のタオル製造機周辺では、静電気に引き寄せられたほこりが大量に出ます。それを商品として販売が出来て、1個が300円程度での販売ですからそうは儲かりませんが、捨てるのにも手間暇が掛かっていました。 漁港でも捨てられていた『珍魚』が、既存外の販売ルートを構築して消費者のところまで届くようになって貢献していますが、捨てるのにも多額の費用が掛かる時代です。捨てるモノを商品にする発想こそが、経営の革新につながっています。「今治のホコリ」は現在はプラスチックの透明感をだした容器で販売されていますが、内容が認知されたら紙容器にして、そのまま火に投入したら、持ち帰ることもなくなる。一石二鳥商品ですね。  |
|
2023,06,26, Monday
25日高松市内リーガホテルゼスト高松で、標題の総会と懇親会が行われました。来賓は大学総務担当常務理事・田部井茂様、校友会副会長・西脇司様、香川県父母の会・宮川英巳様、今年の全国愛知大会幹事・中村一樹様をお迎えし、文字通り『通常総会』として行われました。大学側は、東京六大学野球部の3季連覇を、支部側は、2024年開催の『全国交友香川大会』に意識が傾注しています。
2020年に計画されていた『第56回全国交友香川大会』が、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い中止となり、香川県支部としては断腸の思いで過ごしておりました。21年第57回福島大会も、22年第58回岡山大会も中止、今年2023年第59回大会が既報のように愛知県名古屋市で行われます。諦めていた香川大会でしたが、大学側の配慮等のお陰で、来年の再挑戦の機会が与えられました。 玉越浩達名誉支部長(前支部長)の働きかけも、大きかったようです。開催に執念を燃やしながら、支部長を図子泰副支部長(50年)に委ね、新体制を構築したのも功を奏したと思います。二人は高松高校時代からの、応援部の先輩後輩の関係です。全国支部長会構成員の中には、『応援団』卒が多くいて、今日の来賓・中村一樹氏も応援団OBでした。人脈の要のようなモノです。 総会で、玉越浩達名誉支部長(前支部長)に学校法人明治大学より感謝状が贈られ、香川明俊先輩と浜口勇氏(41年政経)のお二人が知事表彰の顕彰を受けていました。浜口勇氏(41年政経)は、小豆島町議を13期51年間務められました。香川明俊氏は、高松栗林ライオンズクラブメンバーでもあり、飲食業功績で、私には近しい先輩の一人であります。 懇親会の最後は、田川健三(46・政経)の『明大節』の一踊り。2014年6月9日に私がユーチューブにアップしたモノが、視聴回数3万回で未だ健在。全国校友香川大会でも、更にバージョンアップして登場することでしょう。この年になって、自分の中で住み分けが始まっています。これからの20年設計の中で、楽しみの節がまた一つ増えました。      |