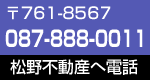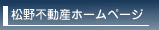|
2023,06,19, Monday
日本郵政とヤマトホールディングは19日、メール便と小型荷物の事業で協業すると発表した。ヤマト運輸が預かった荷物を、日本郵便の配達網で顧客まで運ぶようになる。物流業界で大手2社が手を組み、ドライバー不足が懸念される『物流の2024年問題』に対応する。報道を見て、結構な構想だと納得する。私が何より気がかりな通販業界の発言は、『送料無料』と言う発言です。
通信販売がますます佳境に入り、老若男女が利用している。私もその一人ですが、『送料無料』と聞くと「じゃー誰が運ぶの」と叫びたくなる。通販が隆盛を極めるのも、流通網、つまりトラックドライバーが活躍してくれているから。その業務が無料と言うのは『能なし』のようにも聞こえる。少なくとの『業者負担』等に、可及的変更を促すべきです。 物流問題で私が一番力説したかったのがそこで、今回の協業提携は当を得ている。トラックドライバーの残業規制強化に伴う24年問題や、環境問題など社会課題の解決を両社ともに真剣に考えている。今でも見かけるようになっているが、ドライバーには一定時間ごとに車を停めて休息が義務付けられている。それが2024年から一層厳しくなる。だからドライバーは、サービスエリアの隅にトラックを停めている。タコメーターの記録が、そのまま労働状況として残るからだ。 一定時間ごとに車を停めて、身体を動かしたり、トイレまで歩くのは良いことだ。法律の趣旨に大賛成だが、それではドライバーが不足し、業務が立ちゆかなくなる。そこで自動運転システムが登場しはじめた。幹線の一部にすぎないが、そこで私はトラックの貨車部分を切り離して運ぶことを提唱する。本格稼働には綿密な計画が必要だが、ざっくり言うと次のように考える。 考え方の原点は、江戸時代の松前船にあり、北海道から出た大型船は、富山湾に入り、港に船を着ける。その船を、別の乗組員組チームが琉球王国まで運ぶ。北海道からのチームは、琉球王国からの船と荷物を受け取り、逆に北海道まで廻船する。この仕組みが、ある期間続いたとモノの本で読んだことがあります。この発想を、トラックに応用したらどうだろうか。今の大型トラックは、運転部分と貨物積載部分が分かれる。 九州四国からの荷物は、大阪のトラックターミナルで別のドライバーに託す。そして東京まで6時間、東京のトラックターミナルでまた別のドライバーが預かった荷物を目的地まで運ぶ。逆のコースも成り立つ。完全自動化になれば、その時はまた考えれば良い。 幹線ルートだけなら鉄道利用も考えられるが、その後の輸送を考えるとやはりトラックが勝る。運転手は休ませて、荷物は動かす。こうすれば、24年問題も効率化の促進で料金体系も無理のない物流体制が出来るのではないだろうか。一番は、ドライバーさんに感謝ですよ。 |